【開催案内】『情報的健康』を、日本から世界へー国際連携によるデジタル空間健全化への駆動ー(2024年12月21日)
■企画趣旨
情報摂取のバランスを意識することなどを通じて、個々人が希求する情報摂取状況を実現すること-「情報的健康」が提唱されてから、数年が過ぎた。しかしながら、情報空間の健全性は好転することはなく、むしろ「アテンション・エコノミー」の進行とともに、悪化しているといわざるを得ない。また、戦争をめぐる偽・誤情報の拡散など、情報空間を巡る問題は、もはや国境を越えており、国際的な枠組みで対応を急ぐことが強く求められている。
本シンポジウムでは、健全な言論空間に関する各国の議論を参照しつつ、国際的な視点から、日本や世界が今後向かうべき言論空間のあり方、そして「情報的健康」という概念それ自体について、さらなる検討を加える。また、本シンポジウムを、情報空間の問題点について、国際的な枠組みによって対応していくにあたって、「情報的健康」を国際的に普及させるとともに、様々な研究や活動を実践していくなど、各国の研究機関・研究者と協働する契機としたい。
■開催概要
日時:2024年12月21日(土)13:00~18:40(開場12:30)
会場:慶應義塾大学三田キャンパス 北館ホール ※途中入退場自由
対象:どなたでもご参加いただけます ※要事前登録
形式:対面とzoom配信のハイブリッド(同時通訳あり)
言語:日本語・英語
参加費:無料
主催:慶應義塾大学X Dignityセンター
後援:Originator Profile技術研究組合、計算社会科学会、人工知能学会、一般財団法人NHK財団
なお、本シンポジウムは、JST-RISTEX『SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム(情報社会における社会的側面からのトラスト形成)』研究開発プログラム「可視化によるトラスト形成:パーソナライズされたデジタル情報空間のリテラシー教育(研究代表者:鳥海 不二夫)」の支援のもと開催いたします。
※イベントポスターはこちら
■参加方法:以下のフォームより事前登録をお申込みください。
https://forms.gle/L71qYJivRi78xAM78
※受付終了2024年12月20日(金)12:00
※会場参加は定員に達した時点で申込みを締め切ります。
■プログラム(敬称略)
※プログラム、講演内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
総合司会:
大木 咲貴子(東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻専門職学位課程)
〈第一部〉13:00〜
13:00-13:05 開会挨拶
山本 龍彦(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)
13:05-13:20 趣旨説明
鈴木 雄也(情報的健康プロジェクト事務局)
13:20-13:25「情報的健康」紹介動画の放映
動画作成:Classroom Adventure
13:25–13:40 基調講演「SNS時代に問われるメディアリテラシー」
古田 大輔(日本ファクトチェックセンター編集長)
13:40-14:20 特別講演①「情報エコシステムの健全性における現在の課題と公衆衛生の枠組みを活用した対策」
Tina D Purnat(ハーバードT.H.Chan公衆衛生大学院 公衆衛生学博士課程/メンフィス大学公衆衛生学部 客員研究員)
14:20-15:00 特別講演②「なめらかな社会と分断社会」
鈴木 健(東京大学特任研究員)
15:00-15:10 休憩
〈第二部〉15:10〜
15:10-15:50 パネルディスカッション①『情報的健康』ー神経科学・認知科学の視点を踏まえて
〈モデレーター〉
山本 龍彦(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)
〈パネリスト〉
牛場 潤一(慶應義塾大学理工学部教授)
徳永 聡子(慶應義塾大学文学部教授)
小久保 智淳(東京大学大学院情報学環助教、KGRI 客員所員)
15:50-17:20 パネルディスカッション②「『情報的健康』の国際連携に向けての課題」
〈モデレーター〉
水谷 瑛嗣郎(関西大学社会学部メディア専攻准教授)
〈パネリスト〉
鳥海 不二夫(東京大学大学院工学系研究科教授)
Tina D Purnat(ハーバードT.H.Chan公衆衛生大学院公衆衛生学博士課程/メンフィス大学公衆衛生学部 客員研究員)
Thitirat Thipsamritkul(タマサート大学法学部講師(国際法センター、日本法研究センター))
水嶋 一憲(大阪産業大学経済学部国際経済学科教授)
鍛治本 正人(香港大学ジャーナリズム・メディア研究センター 教授)
17:20-17:45 休憩
〈第三部〉17:45〜
17:45-18:35 情報的健康に関する国際学術連携に向けた合意
山本 龍彦(慶應義塾大学大学院法務研究科教授)
水嶋 一憲(大阪産業大学経済学部国際経済学科教授)
鍛治本 正人(香港大学ジャーナリズム・メディア研究センター教授)
Dongsheng Zang(ワシントン大学)
Katarzyna Kubuj(ポーランド科学アカデミーフランス・ポーランド法思想研究センター)
Caroline Lequesne(コートダジュール大学)
Thitirat Thipsamritkul(タマサート大学法学部講師(国際法センター、日本法研究センター))
18:35-18:40 閉会挨拶
山口 寿一(株式会社読売新聞グループ本社代表取締役社長、慶應義塾大学X Dignityセンター・アドバイザリーボード議長)
■登壇者紹介
山本 龍彦
慶應義塾大学大学院法務研究科教授、慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)副所長、X Dignityセンター共同代表
 慶應義塾大学法学部卒業、同大学院法学研究科博士課程単位取得退学、博士(法学)。ワシントン大学ロースクール客員教授、司法試験考査委員等を歴任。現在、内閣府消費者委員会委員、デジタル庁・経済産業省「国際データガバナンス検討会」座長、総務省「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」構成員などを務める。主な著書に『アテンション・エコノミーのジレンマ』(KADOKAWA)、『<超個人主義』>の逆説――AI社会への憲法的警句』(弘文堂)、『デジタル空間とどう向き合うか』(日経BP、共著)、『AIと憲法』(日本経済新聞出版社、編著)など。
慶應義塾大学法学部卒業、同大学院法学研究科博士課程単位取得退学、博士(法学)。ワシントン大学ロースクール客員教授、司法試験考査委員等を歴任。現在、内閣府消費者委員会委員、デジタル庁・経済産業省「国際データガバナンス検討会」座長、総務省「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」構成員などを務める。主な著書に『アテンション・エコノミーのジレンマ』(KADOKAWA)、『<超個人主義』>の逆説――AI社会への憲法的警句』(弘文堂)、『デジタル空間とどう向き合うか』(日経BP、共著)、『AIと憲法』(日本経済新聞出版社、編著)など。
鈴木 雄也
情報的健康プロジェクト事務局
 横浜国立大学を卒業後、中京テレビ放送に就職。報道記者として政治家や著名人など300人以上を取材し、1,000本以上のニュース制作に携わる。その後異動した営業部門では担当領域における過去最高売上を達成し、社内表彰を受賞。その後外資系ウェブメディアへ転職し、ウェブディレクターとして複数のナショナルクライアントとのタイアップコンテンツの企画・制作に携わった後、新聞社へ入社。テレビ、ウェブ、新聞とメディア業界を渡り歩き、様々な業務を経験する中で、あらゆるメディアがPVなどの「数字」に支配されつつある現状に疑問を抱き、ライフワークとして2022年より本プロジェクトに参画。
横浜国立大学を卒業後、中京テレビ放送に就職。報道記者として政治家や著名人など300人以上を取材し、1,000本以上のニュース制作に携わる。その後異動した営業部門では担当領域における過去最高売上を達成し、社内表彰を受賞。その後外資系ウェブメディアへ転職し、ウェブディレクターとして複数のナショナルクライアントとのタイアップコンテンツの企画・制作に携わった後、新聞社へ入社。テレビ、ウェブ、新聞とメディア業界を渡り歩き、様々な業務を経験する中で、あらゆるメディアがPVなどの「数字」に支配されつつある現状に疑問を抱き、ライフワークとして2022年より本プロジェクトに参画。
Classroom Adventure(動画作成)


学びを楽しくする「ゲーミフィケーション」をテーマにしたクリエイティブファームとして、教育機関や企業研修など幅広い分野で新しい学びの体験を提供している。2022年のGoogle主催ファクトチェック世界大会Youth Verification Challengeで日本優勝、 世界4位を獲得したメンバーが中心となり、体験型メディアリテラシープログラム「Ray’s Blog」を開発。動画、投稿に潜むフェイクの見抜き方など、楽しくメディアリテラシー教育を学べる謎解きプログラムとして、現在では世界5カ国(カナダ、インドネシア、日本、台湾、アメリカ)の学校で導入、各地の小中高学校で出張授業を開催している。朝日新聞社主催 大学SDGs ACTION! AWARDS 2024一般部門でグランプリ受賞。Google Trusted Media Summit 2023、総務省「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」にて発表。
古田 大輔
ジャーナリスト/メディアコラボ代表、日本ファクトチェックセンター(JFC)編集長、デジタル・ジャーナリスト育成機構(D-JEDI)事務局長
 早稲田大政経学部卒。朝日新聞記者、BuzzFeed Japan創刊編集長を経て独立し、ジャーナリストとして活動するとともに報道のDXをサポート。2020-2022年にGoogle News Labティーチングフェローとして延べ2万人超の記者や学生らにデジタル報道セミナーを実施。2022年9月に日本ファクトチェックセンター編集長に就任。その他の主な役職として、デジタル・ジャーナリスト育成機構事務局長など。早稲田大、慶應大、近畿大で非常勤講師。ニューヨーク市立大院ジャーナリズムスクール News Innovation and Leadership 2021修了。
早稲田大政経学部卒。朝日新聞記者、BuzzFeed Japan創刊編集長を経て独立し、ジャーナリストとして活動するとともに報道のDXをサポート。2020-2022年にGoogle News Labティーチングフェローとして延べ2万人超の記者や学生らにデジタル報道セミナーを実施。2022年9月に日本ファクトチェックセンター編集長に就任。その他の主な役職として、デジタル・ジャーナリスト育成機構事務局長など。早稲田大、慶應大、近畿大で非常勤講師。ニューヨーク市立大院ジャーナリズムスクール News Innovation and Leadership 2021修了。
Tina D Purnat
ハーバードT.H.Chan公衆衛生大学院 公衆衛生学博士課程、メンフィス大学公衆衛生学部 客員研究員
 リード大学経済学の学士号、オレゴン健康科学大学生物医療情報学・臨床疫学の修士号を取得。医療・健康情報学の専門家であり、欧州疾病予防管理センター(ECDC)、WHO欧州地域事務所、WHO本部などで、健康情報やデジタル公衆衛生のリーダーとして活動してきた。現在、オセアニア地域デジタルヘルス協会特別研究員、メンフィス大学公衆衛生学部客員研究員を務める。EUPHAヘルスリテラシー部門、WFPHAのグローバルヘルスエクイティとデジタル技術に関するワーキンググループ、WHOの健康要因専門グループの運営委員会に所属し、JMIR InfodemiologyやBMC Public Healthの編集員、WHOのワクチン・セーフティ・ネット諮問委員も務める。COVID-19パンデミック中にはインフォデミック管理分野を切り開き、140カ国から1,400人以上が参加するWHOのグローバルネットワークを構築。
リード大学経済学の学士号、オレゴン健康科学大学生物医療情報学・臨床疫学の修士号を取得。医療・健康情報学の専門家であり、欧州疾病予防管理センター(ECDC)、WHO欧州地域事務所、WHO本部などで、健康情報やデジタル公衆衛生のリーダーとして活動してきた。現在、オセアニア地域デジタルヘルス協会特別研究員、メンフィス大学公衆衛生学部客員研究員を務める。EUPHAヘルスリテラシー部門、WFPHAのグローバルヘルスエクイティとデジタル技術に関するワーキンググループ、WHOの健康要因専門グループの運営委員会に所属し、JMIR InfodemiologyやBMC Public Healthの編集員、WHOのワクチン・セーフティ・ネット諮問委員も務める。COVID-19パンデミック中にはインフォデミック管理分野を切り開き、140カ国から1,400人以上が参加するWHOのグローバルネットワークを構築。
鈴木 健
東京大学特任研究員
 1998年慶應義塾大学理工学部物理学科卒業。2009年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。専門は複雑系科学、自然哲学。「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」ことをミッションに、2012年にスマートニュース株式会社を共同創業。代表取締役会長。2014年9月SmartNews International Inc.を設立し、米国市場の展開を牽引している。著書に 『なめらかな社会とその敵』など。
1998年慶應義塾大学理工学部物理学科卒業。2009年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。専門は複雑系科学、自然哲学。「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」ことをミッションに、2012年にスマートニュース株式会社を共同創業。代表取締役会長。2014年9月SmartNews International Inc.を設立し、米国市場の展開を牽引している。著書に 『なめらかな社会とその敵』など。
©︎新津保建秀
牛場潤一
慶應義塾大学理工学部教授、X Dignityセンター共同代表
 2001年、慶應義塾大学理工学部卒。2004年に博士(工学)を取得。2022年より教授。研究成果活用企業株式会社LIFESCAPES(’19〜)の代表取締役社長を兼務。The BCI Research Award 2019, 2017, 2013, 2012, 2010 Top 10-12 Nominees、文部科学省「平成27年度若手科学者賞(ブレイン・マシン・インターフェースによる神経医療研究)ほか、受賞多数。脳が本来持つ「やわらかさ」に着目し、一人ひとりが豊かで人間らしい日々を過ごすためのテクノロジーの創造を目指し、脳と機械を接続して身体運動を補助するブレイン・マシン・インターフェース技術(BMI)の基礎研究から応用研究、医療機器開発までを、一気通貫で取り組んでいる。
2001年、慶應義塾大学理工学部卒。2004年に博士(工学)を取得。2022年より教授。研究成果活用企業株式会社LIFESCAPES(’19〜)の代表取締役社長を兼務。The BCI Research Award 2019, 2017, 2013, 2012, 2010 Top 10-12 Nominees、文部科学省「平成27年度若手科学者賞(ブレイン・マシン・インターフェースによる神経医療研究)ほか、受賞多数。脳が本来持つ「やわらかさ」に着目し、一人ひとりが豊かで人間らしい日々を過ごすためのテクノロジーの創造を目指し、脳と機械を接続して身体運動を補助するブレイン・マシン・インターフェース技術(BMI)の基礎研究から応用研究、医療機器開発までを、一気通貫で取り組んでいる。
徳永聡子
慶應義塾大学文学部教授、X Dignityセンター共同代表
 慶應義塾大学文学部卒業。同大学大学院文学研究科博士課程修了。PhD(文学)。ケンブリッジ大学コーパス・クリスティ客員研究員(2010年10月-2011年9月)、ハンティントン図書館客員研究員(2012年夏)専門は中世イギリス文学、書物史。著書に『神・自然・人間の時間―古代・中近世のときを見つめて』、『旅するナラティヴ―西洋中世をめぐる移動の諸相』、Caxton’s Golden Legend, EETS OS 355, 357など。
慶應義塾大学文学部卒業。同大学大学院文学研究科博士課程修了。PhD(文学)。ケンブリッジ大学コーパス・クリスティ客員研究員(2010年10月-2011年9月)、ハンティントン図書館客員研究員(2012年夏)専門は中世イギリス文学、書物史。著書に『神・自然・人間の時間―古代・中近世のときを見つめて』、『旅するナラティヴ―西洋中世をめぐる移動の諸相』、Caxton’s Golden Legend, EETS OS 355, 357など。
小久保 智淳
東京大学大学院 情報学環 助教、慶應グローバル・リサーチ・インスティテュート 客員所員
 慶應義塾大学法学部卒業。同大学大学院法学研究科修士課程・理工学研究科修士課程を修了し、法学・理学双方の修士号を取得したのち、同法学研究科博士課程単位取得退学。国立国会図書館調査及び立法考査局憲法課 非常勤調査員、慶應義塾大学大学院法学研究科研究員などを経て2024年度より現職。2022年度科学技術社会論・柿内賢信記念奨励賞、第13回日本学術振興会育志賞を受賞。神経科学と法学の融合領域である神経法学(neurolaw)について、特に「認知過程の自由(cognitive liberty)」、「神経権(neurorights)」を重点領域として研究を行っている。
慶應義塾大学法学部卒業。同大学大学院法学研究科修士課程・理工学研究科修士課程を修了し、法学・理学双方の修士号を取得したのち、同法学研究科博士課程単位取得退学。国立国会図書館調査及び立法考査局憲法課 非常勤調査員、慶應義塾大学大学院法学研究科研究員などを経て2024年度より現職。2022年度科学技術社会論・柿内賢信記念奨励賞、第13回日本学術振興会育志賞を受賞。神経科学と法学の融合領域である神経法学(neurolaw)について、特に「認知過程の自由(cognitive liberty)」、「神経権(neurorights)」を重点領域として研究を行っている。
水谷 瑛嗣郎
関西大学社会学部メディア専攻准教授 同志社大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学、博士(法学)。帝京大学法学部助教を経て2019年より現職。慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート客員所員、日本ファクトチェックセンター運営委員、総務省公共放送ワーキンググループ、同デジタル広告ワーキンググループ構成員などを務める。編著に『リーディング メディア法・情報法』(法律文化社、2022年)共著に『Liberty2.0』(弘文堂、2023年)、『憲法学の現在地』(日本評論社、2020年)、『AIと憲法』(日本経済新聞出版社、2018年)他
同志社大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学、博士(法学)。帝京大学法学部助教を経て2019年より現職。慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート客員所員、日本ファクトチェックセンター運営委員、総務省公共放送ワーキンググループ、同デジタル広告ワーキンググループ構成員などを務める。編著に『リーディング メディア法・情報法』(法律文化社、2022年)共著に『Liberty2.0』(弘文堂、2023年)、『憲法学の現在地』(日本評論社、2020年)、『AIと憲法』(日本経済新聞出版社、2018年)他
鳥海 不二夫
東京大学大学院工学系研究科教授
 2004年東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム工学専攻博士課程修了(博士(工学))、同年名古屋大学情報科学研究科助手、2007年同助教、2012年東京大学大学院工学系研究科准教授、2021年同教授。計算社会科学、人工知能技術の社会応用などの研究に従事。計算社会科学会副会長、情報法制研究所理事。電子情報通信学会、情報処理学会、日本社会情報学会、AAAI各会員。科学技術への顕著な貢献2018(ナイスステップな研究者)。主な著書に「強いAI・弱いAI 研究者に聞く人工知能の実像」「人狼知能 だます・見破る・説得する人工知能」「計算社会科学入門」。
2004年東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム工学専攻博士課程修了(博士(工学))、同年名古屋大学情報科学研究科助手、2007年同助教、2012年東京大学大学院工学系研究科准教授、2021年同教授。計算社会科学、人工知能技術の社会応用などの研究に従事。計算社会科学会副会長、情報法制研究所理事。電子情報通信学会、情報処理学会、日本社会情報学会、AAAI各会員。科学技術への顕著な貢献2018(ナイスステップな研究者)。主な著書に「強いAI・弱いAI 研究者に聞く人工知能の実像」「人狼知能 だます・見破る・説得する人工知能」「計算社会科学入門」。
Thitirat Thipsamritkul
タマサート大学法学部講師(国際法センター、日本法研究センター)
 京都大学法学部卒業、神戸大学大学院国際協力研究科およびロンドン大学東洋アフリカ研究学院(SOAS)で法学修士(LLM)を取得。公共国際法、人権法、メディア法、法とテクノロジー技術を専門とする。市場、技術、人権の相互関係に関心を持ち、特に表現の自由、プライバシー、インターネットガバナンスの分野で研究を行っている。また、市民社会や公共部門と協力し、タイの個人データ保護法やデジタルプラットフォームやAIガバナンスをはじめとする立法や政策の改善にも積極的に関与している。2020-2023年にはアムネスティ・インターナショナル・タイ支部の理事長を務め、現在は国際理事会の会員のメンバーとして、国際人権組織のガバナンスに力を入れている。
京都大学法学部卒業、神戸大学大学院国際協力研究科およびロンドン大学東洋アフリカ研究学院(SOAS)で法学修士(LLM)を取得。公共国際法、人権法、メディア法、法とテクノロジー技術を専門とする。市場、技術、人権の相互関係に関心を持ち、特に表現の自由、プライバシー、インターネットガバナンスの分野で研究を行っている。また、市民社会や公共部門と協力し、タイの個人データ保護法やデジタルプラットフォームやAIガバナンスをはじめとする立法や政策の改善にも積極的に関与している。2020-2023年にはアムネスティ・インターナショナル・タイ支部の理事長を務め、現在は国際理事会の会員のメンバーとして、国際人権組織のガバナンスに力を入れている。
水嶋 一憲
大阪産業大学経済学部国際経済学科教授
 専攻はメディア文化研究、社会思想史。京都大学経済学部卒・同大学院経済学研究科修士課程修了・同博士課程単位取得退学。2003年〜2004年、デューク大学アジア太平洋研究所客員研究員。2012年〜2013年、ハーヴァード大学ライシャワー日本研究所客員研究員。主な著書に『コミュニケーション資本主義と〈コモン〉の探求』(共著、東京大学出版会、2019年)、『メディア論の冒険者たち』(共著、東京大学出版会、2023年)、『プラットフォーム資本主義を解読する』(共編著、ナカニシヤ出版、2023年)、訳書にネグリ=ハートの〈帝国〉3部作および『アセンブリ』(共訳、岩波書店、2022年)などがある。
専攻はメディア文化研究、社会思想史。京都大学経済学部卒・同大学院経済学研究科修士課程修了・同博士課程単位取得退学。2003年〜2004年、デューク大学アジア太平洋研究所客員研究員。2012年〜2013年、ハーヴァード大学ライシャワー日本研究所客員研究員。主な著書に『コミュニケーション資本主義と〈コモン〉の探求』(共著、東京大学出版会、2019年)、『メディア論の冒険者たち』(共著、東京大学出版会、2023年)、『プラットフォーム資本主義を解読する』(共編著、ナカニシヤ出版、2023年)、訳書にネグリ=ハートの〈帝国〉3部作および『アセンブリ』(共訳、岩波書店、2022年)などがある。
鍛治本 正人
香港大学ジャーナリズム・メディア研究センター 教授
 社会学博士。専門はアジアにおける誤情報、虚偽情報の生態系研究、ファクトチェック実践、ニュースリテラシー教育。2019年にANNIEと呼ばれるアジア地域の報道の自由、メディア関連法案などを念頭に置いた教育NPOを設立し、各国の教育者、ジャーナリストと協力して教材の開発を行っている。大学では国際ファクトチェック・ネットワーク(IFCN)承認加盟団体であるアニー・ラボ(Annie Lab)を主導している。2024年4月、IFCNの諮問委員に就任。
社会学博士。専門はアジアにおける誤情報、虚偽情報の生態系研究、ファクトチェック実践、ニュースリテラシー教育。2019年にANNIEと呼ばれるアジア地域の報道の自由、メディア関連法案などを念頭に置いた教育NPOを設立し、各国の教育者、ジャーナリストと協力して教材の開発を行っている。大学では国際ファクトチェック・ネットワーク(IFCN)承認加盟団体であるアニー・ラボ(Annie Lab)を主導している。2024年4月、IFCNの諮問委員に就任。
■情報的健康事務局スタッフ
東京大学大学院法学政治学研究科
法曹養成専攻2年 大木咲貴子

慶應義塾大学法学部
法律学科3年 清水かれん
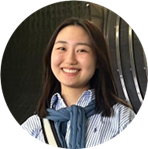
慶應義塾大学法学部
政治学科3年 簗場元就

慶應義塾大学法学部
法律学科3年 南祐翔

今後、生成AIをはじめとする先端技術がさらに発達、定着していく中で、「情報的健康」は新たな発想だと感じ、関心を持ちました。現状の言論空間について、全世代が考え直さねばならない岐路にあると感じております。各個人が情報空間を上手に利用していくにはどうすべきか、この事務局に携わる中で考えていきます。
関西大学社会学部
社会学科メディア専攻4年 竹内優衣

前回シンポジウムに参加したご縁から、この度事務局員として携わらせていただくことになりました。スマートフォンやSNSが勉強、仕事、余暇、睡眠といったあらゆる場面において密接に関連していることを日々感じています。「情報的健康」がこれまで以上に広く意識される契機となるよう、尽力してまいります。
関西大学社会学部
社会学科メディア専攻4年 中野惣介

水谷先生のゼミで学ぶ中で「情報的健康」に興味を持つようになりました。SNSや広告で溢れる現代、つい刺激的な情報に引き寄せられがちな中で、バランスよく多様な情報に触れることの大切さをこのシンポジウムの事務局に関わる中で実感しています。これからの社会で、どうしたらより良い情報環境を作れるのか考えていきたいです。
■お問い合わせ
慶應義塾大学 X Dignityセンター「アテンション・エコノミーと情報的健康」サブユニット事務局
info-health-group[at]keio.jp ←[at]を半角のアットマークに直して送信してください。
