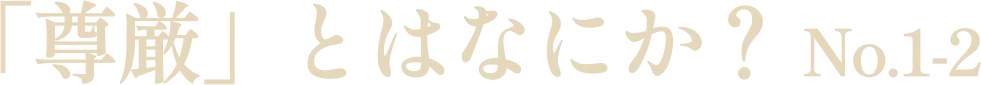銃口の前で尊厳は有効か?


駒村 圭吾
X Dignity センター運営委員会委員長、慶應義塾大学法学部教授
X Dignityセンターが立ち上がり、1年が経った。慶應義塾の研究者ならびに志のある代表的企業の方たちが、このトポスに集結し、その輪は現在も広がり続けている。
それぞれの参加者は「尊厳」という概念になんらかの思い入れがあって参集したはずである。そうであってほしいし、また、そうでなければならない。そして、このように断定する以上、当の私自身がどうしてこのセンターに惹かれたのかをまずは告白しておかなければならないだろう。
1年前、「尊厳」ときいて私がまっさきに思い浮かべたのが、タイトルに掲げた次の発問である。≪銃口の前で「尊厳」は有効か?≫
「ウクライナで、そしてガザで、残酷で絶望的な光景が繰り広げられる中、私は、この問いを発せざるを得なかった……」と告白すれば、おそらく分かりやすいし、共感もしていただけるだろう。しかし、実は、この発問の背景はもっとフクザツである。
上述の発問は、1964年にサルトルが発した言葉がきっかけとなって広がり、論争の的になったある発問と相似形をなしている。それは、≪飢えて死んでいく子供たちの前で「文学」は有効か?≫という問いである。当然であるが、餓死寸前の子供に文学は無力である。サルトル自身も餓死寸前の子供に『嘔吐』は無力であると述べており、だから文学者は文学を一時捨ててでも子どもたちの側に立って行動すべきだと説いた。もちろん、「文学が無力であるわけがない」、「文学は固有の力を持っている」等々の反発が起きることをサルトルは想定していただろう。
これと同じように、≪銃口の前で「尊厳」は有効か?≫と問われれば、当然それは無力である。泣きわめこうが、祈ろうが、ゴマをすろうが、何をしても意味はなく、引き金は引かれる。どっちみち殺されるのだから、せめて尊厳ある殺され方を望んだとしても、理不尽な殺害そのものの尊厳破壊性は消えない。いずれにしても無力なのだ。
このように、二つの発問は同型に見える。が、よく考えてみると、その内容は同じではなく、むしろ対照的ですらある。≪飢えて死んでいく子供たちの前で「文学」は有効か?≫は、「政治」が解決すべき問題を「文学」で解決できるか?という問いであり、本来スジの違う営みを敢えて対置させている。だから無力であるという回答がもたらされるのは半ば必然的なのである。そして、「無力」を自覚することは、同時に、それを超えて、文学固有の力を再発見させる方向に向かわせる可能性があるが、他方で、「無力」であることに甘んじて、文学が固有に果たし得る責務を放棄させる方向に流れるかもしれない。
この極めて危うい問いと回答は、一見すると、≪銃口の前で「尊厳」は有効か?≫にも当てはまりそうだ。しかし、文学については成立する「政治」と「文学」のムリ筋の対置がここでは成立しない。「尊厳」という概念は、「文学」とは異なり、法制度の最も基層を支える法概念であるからだ。つまり、「政治」と「尊厳」を対置することはムリ筋ではない。「尊厳」は法制度を通じて「政治」とまさしく対峙すべき関係にある。だから、無力であっていいわけがない。「尊厳」が果たすべき固有の責務を放棄する方向に出ることも許されない。「尊厳」に固有の力を再発見するという方向での回答しか、この発問に対しては許されないのである。
≪個人の尊重≫と≪個人の尊厳≫
私は法学部に在籍する研究者で、憲法学を専攻する者である。ご存知の方も多いと思うが、「個人の尊厳」は、「個人の尊重」と並んで、憲法学最大のキラーコンテンツとしてリスペクトされてきた(「尊厳」と「尊重」は一字違いなので混同注意)。そして、決定的なのは、両方とも日本国憲法の中に条文根拠を持つという事実である。条文を確認しておこう。まず、「個人の尊重」について。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
そして、次に「個人の尊厳」について。
第24条 ①婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
「個人の尊重」を規定する13条は、「国民の権利及び義務」のチャプターの冒頭付近、いわば人権編のメインゲートに位置づけられている。他方で、「個人の尊厳」は人権チャプターの中間地点にある家族条項の中に顔を出す。配置上の問題は後に触れるとして、ここでは「個人の尊重」と「個人の尊厳」の関係性について概観しておきたい。
憲法学者の中には、「個人の尊重」と「個人の尊厳」を互換的に用いる人も多い。また、「個人の」ではなく「人間の尊厳」という言葉も多々用いられる。が、他方で、「人間の尊重」という言い方はあまり耳にしない。そうなると、「尊厳」はindividualにもhuman全体にも妥当するが、「尊重」はあくまでindividualな何かを対象としていると言えよう。
ちょっとムズカシイ話しになりかけた。ストレートに整理しよう。13条の「個人の尊重」とは、個人の自己決定に対する尊重である。ある個人がなした人格的決定に対しては国家はしっかりとこれを尊重して、保障する。しつこく言えば、「個人」として「尊重」されるから、個人の自己決定も「尊重」され、それに基づくあらゆる権利主張も「尊重」される。そして、自己決定が「尊重」されることの反転として、自己決定が生み出す結果もすべて「個人」に帰責される。
これに対して、「個人の尊厳」(ヨーロッパではよく使われるが日本国憲法には定めのない「人間の尊厳」も含めて)は、「個人の尊重」との関係でどのような位置に立つのか。それはおそらく次のような関係であろう。個人が自己決定し、自己責任を負うことを承認しているからと言っても、やってはならないことがある。いくら自己決定してもいくら自己責任を負うといっても、超えてはならない規範として「個人の(人間の)尊厳」がある。科学者が自己決定したとしても、そして科学にはそれが技術的に可能だとしても、人間のクローンの創造に踏み出す前にいったん立ち止まることが要求される。いくら自己決定したとしても、そしてそれが最終的な解放につながるとしても、自殺や積極的安楽死の前には踏みとどまることが求められる。
このように、「個人の尊厳」は「個人の尊重」と対峙する関係にある。先に引用した13条の条文に照らせば、「個人の尊厳」は、「公共の福祉に反しない限り」という文言に言うところの「公共の福祉」の一要素をなしていると言えるだろう。これについて、「いや、『個人の尊厳』は『個人の尊重』と対立するのではなく、それを支える正当化根拠ではないか?」と反問する向きもあるだろう。そう考えるとしても、否、そう考えるならばむしろ、根拠はそれを支えている概念を正当化すると同時に枠づける役目も果たすから、両者が対峙する関係にあることには変わりなく、ただそれが根拠に照らした正当化の論証の中に解消されているので表に出てこないだけのことである。
≪個人の尊厳≫と家族条項 ――受精卵の尊厳、仏壇の尊厳、ペットの尊厳
このように両者の関係を整理すると、「個人の尊厳」が、どうして13条というメインゲートではなく、入場した会場に散在するひとつのパビリオンである24条2項にひっそりと掲げられているのか、その理由も分かる。
先に引いたように24条は「家族」や「婚姻」に関する条項である。家族は両性の「自己決定」によって成立する共同体であり、その意味では間違いなく「個人の尊重」の対象になるものである。しかし、「家族」の中には、自律的な意思を持たず、したがって自己決定をすることがそもそも不可能な存在やモノがたくさん連なっている。遺伝子、受精卵、胎児、植物状態や脳死状態の家族、仏壇・位牌・遺骨、墓、家族アルバム、ペット、等々。
これらは、当然のことであるが、意思表示もできないし、自己決定もできない。何かを訴え、要求することもままならない。なので、「個人の尊重」の対象にならず、権利保障もされない。まさに「尊厳」によってその法的処置を考えるべき対象なのである。24条2項は確かに「家族」を対象とするものであるが、上記のような「尊厳」が担当すべき存在やモノの多くは「家族」という絆の広がりの中でこそ生み出される。24条2項の含蓄は深い。
そうなると、憲法学者は、「遺伝子の尊厳」、「受精卵の尊厳」、「胎児の尊厳」、「仏壇の尊厳」、「家族アルバムの尊厳」、「ペットの尊厳」等々について回答を出さなければならない。関連して、「生の尊厳」、「死の尊厳」、「性の尊厳」も当然射程に入れなければならないだろう。そして、以上の尊厳論は、憲法学だけで答えの出せるものではない。医学や生物学をはじめとする自然科学、それを実装する科学技術、憲法以外の法律学はもちろん広く人文社会学の諸学知を動員しないとどうにもならない。私が、XDignityセンターに興味と関心をもってコミットしている理由はもうこれでお分かりだろう。助けてもらわなければどうにもならないからである。
冒頭の問いに戻って ――畏怖の感覚を呼び戻す
やりたいし、またやれることだから、それをやる権利を保障するのが「個人の尊重」であるとすれば、やりたいからと言って、また、やれるからと言っても、やってはならないと命ずるのが「個人の尊厳」である。「尊厳」とは、≪思い止まらせる力≫であり、≪今見える景色を一変させる力≫である。
ロナルド・ドゥオーキンという法哲学者が『いのちの領分』(Ronald Dworkin, Life’s Dominion (Knopf, 1993))という書物において、生命倫理の諸問題を論じている。そこでは、dignityとsanctity(聖性)やinviolability(不可侵性)が互換的に用いられているが、いずれも「内在的価値(intrinsic value)」を問題にするものであるとされる(同書235-236頁)。手段化されない価値を重視する点で、基本的にカントの尊厳論に立つものである。この本の中で、ドゥオーキンはとても興味深いことを言っている。彼は、レンブラントの絵に価値があるのは、それを鑑賞することによって帰結される何かに価値があるのではなく、その絵自体に価値があるからであり、「その絵が壊されると考えるだけでも私たちを恐怖させる(horrifies us)」と言う(同書72頁)。
「尊厳」とは、「内在的価値」を持つものが、その破壊者に対して「恐怖」や「畏怖」の感情を呼び戻すことを要請する規範である。≪銃口の前で「尊厳」は有効か?≫の発問に立ち返れば、銃口を向け引き金を引こうとする者が眼前の一己の生に宿る何かを畏怖する感情を取り戻すことができるか、≪思いとどまらせる力≫を宗教の力を借りずに法制度や文明が喚起できるかどうか。答えはそれに依存する。さらに、銃口を向けて引き金を引こうとする者がホロコーストの被害者で、殺害されようとする人物がナチスであった場合はどうか。引き金を引く行為は、不条理に奪われた家族や友人の生の尊厳を回復する行為かもしれない。しかし、そのような行為であったとしても、否、そのような背景があるからこそ、思い止まるべきではないか…云々。「尊厳」は≪今見える景色を一変させる力≫も持つ。
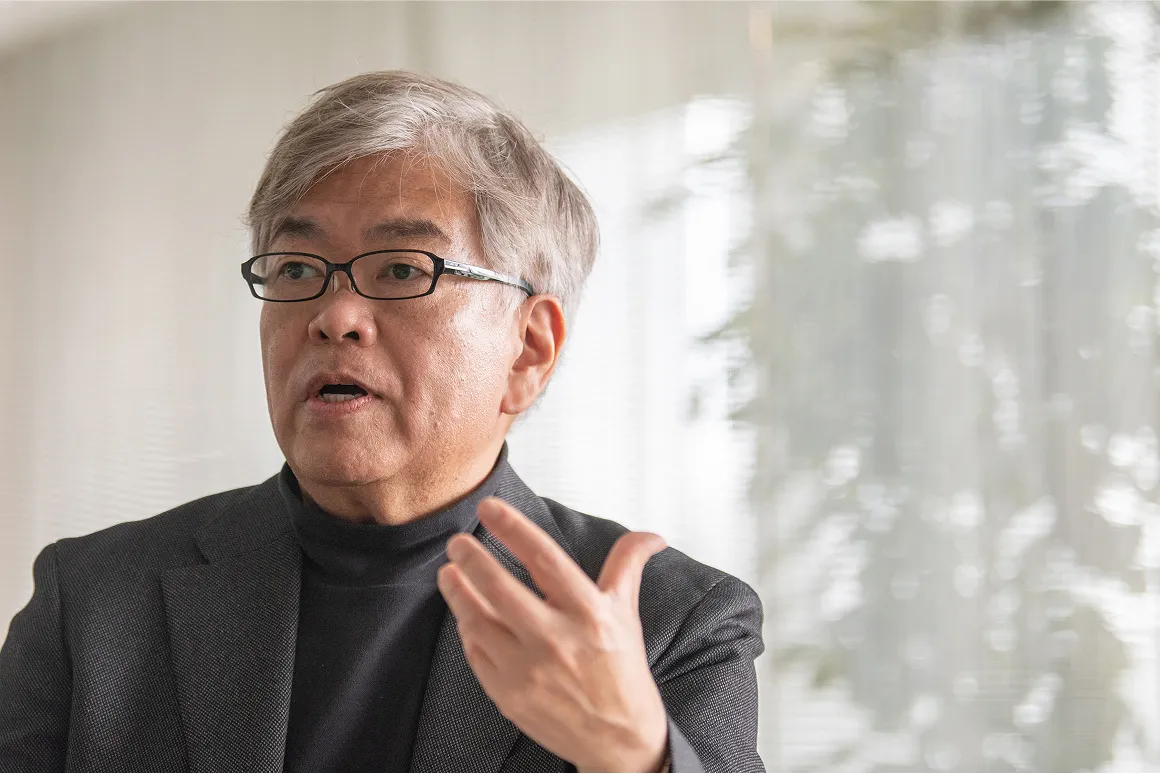
※一部画像はイメージです(生成AIを利用して制作しています)